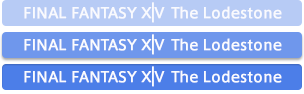「小さな賭けの勝者」
ギラバニア湖畔地帯の冷めた風に乗せて、兵の誰かが口ずさむ歌が聞こえてきた。
「賭けに勝てりゃ この箱 金庫。賭けに負けりゃ この箱 棺」
ひと昔前に砂の都「ウルダハ」で流行った大衆歌の一節である。一攫千金を夢見て、大箱を引きずりながらウルダハを目指す、陽気な男を描いた歌だ。その箱は、賭けに勝てば金庫に、負ければ自分が入る棺となる。生きるか死ぬか運命の骰を投げるため、男は意気揚々と荒野を歩み続ける。
結局、歌の主人公は賭けに勝てたのだろうかと、ピピン・タルピン少闘将は、常々、疑問に思ってきた。なにせこの歌は、父の十八番であり、幼い頃から幾度となく聞かされてきたのだ。ここで言う父とは、義父ラウバーン・アルディンのことではない。血のつながった実父の方だ。
ピピンの父は、お世辞にも良い親ではなかった。いや、息子にとっては最悪の存在だった。大酒飲みで賭け事を好み、借金苦の果てに息子を売ったのだから。これは比喩表現などではない、本当に剣闘試合の興行師に売ったのである。ある日、鉱山で石の選別作業を手伝っていた12歳のピピン少年の前に、剣闘士上がりの屈強な興行師が現れてこう告げた。
「来い、小僧! お前が生きるか死ぬか、賭けをしようじゃないか!」
かくして、剣闘士宿舎の石造りの狭い部屋がピピンの新たな寝床となり、労働と訓練に明け暮れる日々が始まった。先輩剣闘士の身の回りの世話を行う小間使いとして、早朝から働きづめ。それが終わると訓練場に赴き、棒と鞭を手にした訓練士の容赦ないしごきを受ける。
唯一、これまでの生活から改善したのは食事だ。身体が資本の稼業ゆえ、多くの掛け金を集め、賞金を持ち帰らせるためにも、肉体作りは重要である。新参者にも、大麦のパンや肉入りのスープなど、まっとうな食事が与えられた。生まれて初めてスパイスを使った手の込んだ料理を食べたのも、この頃のことである。
それでもやはり、幼さを残す少年には辛い日々であった。いつまで、この生活に耐えられるだろう。仮に耐えられたとて、剣闘試合に出されれば生き残れる保証はない。誘拐同然に連れてこられてから、ピピンは逃げる隙を窺い続けたが、訓練士の警戒が緩むことはなかった。そうして1年ほどが過ぎた頃、主である興行師の命令で、とある熟練剣闘士の付き人を命じられることになる。これが後に、彼の義父となる男との出会いであった。
「若いな、歳はいくつだ?」
開口一番の問いに、ピピンはただ「13」とだけ答えた。その後は、コロセウムの控室に赴くまで、特に言葉を交わしていない。寡黙な男なのだろうか、あるいは試合前の緊張か。ともかくピピンからも、声をかけることはしなかった。剣闘士には気性の荒い者も少なくない。無駄口を叩いて機嫌を損ね、殴られるのはご免だ。
控室に到着してからも、大柄の剣闘士は、二、三の指示を与えただけで、言葉数は少なかった。ピピンは、ただその命に従い鎧の着用を助け、最後に黒鉄の兜を差し出した。大男は、牡牛の頭部を模したその兜を受け取ると、深々と被って舞台へと向かう。

「アラミゴの猛牛、ラウバァァァーン・アルディィィィィン!」
触れ役が、よく通る声で紹介するや、控室に地鳴りのような音が轟いた。観客たちが怒号と歓声をあげているのだ。あの寡黙な男ひとりが登場するだけで、コロセウム全体がこうも沸き立つ。ピピンにとっては衝撃であった。
それから何度もラウバーンの付き添い役を務めた。彼は口数が少なかったが、それでも次第に会話をするようになり、いつしか互いの身の上話をするほどにまでなった。ラウバーンがアラミゴという異国の出身であること、ガレマール帝国と戦い戦功を挙げ、そして、負傷したこと。祖国で起こった革命と、その直後の帝国侵攻。痛む足を引きずりながら、故郷を脱して荒野を彷徨い、たどりついた先のウルダハにて間諜の疑いをかけられ拘束されたこと。今では自由を掴むため、獄門剣闘士として戦っているのだと知ったときには、驚いたものだ。
これほどまでに強く、人々を惹きつけて止まない人物が自分の意志によらず、強いられて戦っているという事実は、妙な話だがピピンにとって希望となった。獄門剣闘士とは、剣闘試合に出場して賞金を得ることで、自らの保釈金を支払い、自由を買おうとする者たちである。ラウバーンは苦しい立場にあっても、己の力で己の道を斬り拓こうとしているのだ。ならば自分も、と思わないではいられない。いつしかピピンは、自ら進んで剣の鍛錬にいそしむようになっていた。生き残り、自由を掴むために。
「これで支払いは終わる。晴れて自由の身というわけだな」
とある試合が終わった後、勝者として控室に戻ってきたラウバーンは、そう言った。
「おめでとうございます、ラウバーン!」
ついにラウバーンは、保釈金を支払い終えたのだ。素直に祝福の言葉を述べたピピンは、はたと気付いた。自由となれば、ラウバーンが剣闘士を続ける理由はない。目標として背を追い続けてきた人物との別れが迫っていると理解した瞬間、ピピンの顔は曇った。
「どうした、嬉しくないのか? 貴様は今日から自由になるのだぞ?」
ラウバーンは、戸惑いの表情を浮かべている。今度は、ピピンが困惑する番だ。
賞金の詰まった革袋を手にした剣闘士と、その付き人の少年が、ふたりそろって困ったような顔をしているのだから、端から見れば滑稽な光景だったろう。ラウバーンは、出会ってからの数ヶ月間、自らの自由を購うためではなく、ピピンの父親が抱えていた借金を返済していたのだ。そして今日の勝利で得た金を以て、支払いが終わるという。
「これでもう、お前が剣闘試合に出る必要はない。
新参者同士が戦う最初の試合は、双方が不慣れなぶん、死人が出ることも多いのだ。
殺されたくもなければ、殺したくもなかろう?」
事情を聞くうちに、ようやく理解が追いついたピピンは、ただただ涙を流した。苦しい生活から解き放たれる喜び、死の恐怖から逃れられた安堵、そして、ラウバーンへの感謝、さまざまな感情が一気に吹き出したのだ。
翌日の早朝、少ない私物を詰めた小さな麻袋を手に、剣闘士宿舎を出るピピンの姿があった。見送りはいない。獄門剣闘士であるラウバーンは独房の中。訓練士も興行師も、ほかの剣闘士たちも、無関係になる少年の門出に興味はないらしい。
まだ太陽の熱で焼かれていない石畳を踏みしめ、ピピンは歩き出した。突然に訪れた自由を噛みしめるように、一歩、また一歩と。だが、人通りのない大通りを歩むうちに、不安感が増す。あのろくでなしの父のことだ、また借金を重ねるに違いない。そして、売れる物があれば息子であろうと売ることは、すでに証明済みなのだ。
ピピンは立ち止まり、そして、駆けだした。来た道を引き返すように。
「どうして、貴様がここにいる?」
独房の前に佇む少年を見て、ラウバーンは言った。ピピンが答える。
「ラウバーン、お願いがあります。もう一度、ボクを剣闘士として鍛えてください!
誰かに救われるんじゃなく、自分の力で、自分の道を斬り拓きたいんです!
あなたのようにッ!」
家に戻れば、ふたたび父に売られかねない。そこが、この剣闘士宿舎よりも良い場所とは限らないだろう。ならば、これまで重ねてきた訓練を活かせる環境で、尊敬する人物の背を追いたい。
少年なりの覚悟を見て取ったラウバーンは、ただ微笑んだ。
その後、ラウバーンが取った行動をピピンは一生忘れないだろう。父がピピンを売り払う時に、興行師が記した契約書を買い取り、八官府に養子縁組の届け出を提出したのである。契約書には、興行師を保護者とすることに同意する旨が記されていたのだ。その記述を盾として、強引に親権を奪い取ったのである。
以降、ピピンは、新たな父の下で暮らすこととなった。獄門剣闘士の義父と、自由人の子が、剣闘士宿舎で暮らすという奇妙な生活の始まりである。ラウバーンは師として、ピピンに剣の稽古を付けた。だが、剣闘士となることは認めず、成人年齢に達してから己の道を決めるようにと諭したのだった。
そして今、傭兵としての経験を積み、25歳の青年になったピピンは、不滅隊の将校として義父の故郷を取り戻そうとしている。
「あの時も生き残ったのです。今回もまた、賭けに勝ってみせますよ、義父上!」
呪剣ティソーナを手に、ピピンは戦場へと駆けだした。