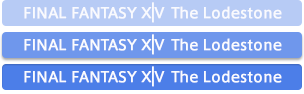「蒼を捨てた竜騎士」
古の遺跡に吹く風は、黄金の輝きを帯びているように感じられた。
魔力を乗せた咆哮を発し、竜詩を紡ぐことを何よりも好んだというかの天竜……詩竜ラタトスクの棲処であったからだろうか。今や竜たちの言葉で「悲しみの詫び言」を意味する「ソール・カイ」と呼ばれる天上の宮殿は、千年の時を経てなお、清涼な魔力で満ちていた。
「許せ、なんて言える立場でもないが、戦いは終わったぜ……」

かつて蒼の竜騎士と呼ばれた男、エスティニアンは竜詩戦争の発端となった「人の裏切り」によって犠牲となった詩竜に向かって、そうつぶやいた。
すると一陣の風が吹き抜け、手向けの花を散らし、宙へと巻き上げた。
『誰かと思えば、蒼の竜騎士であったか……』
突然、魔力に乗せられた強烈な意思が、頭の中に響き渡る。続いて、竜の羽ばたきを感じて振り向いたエスティニアンが見たのは、詩竜と同じく七大天竜に数えられる存在、聖竜フレースヴェルグであった。
「チッ……」
雲廊での決戦で、かの英雄に救われたエスティニアンは、親友アイメリクの貴族院議長就任を見届けると、そのままひっそりと皇都から姿を消した。むろん、友の支えとなり新たな門出を迎えた国のために働くべきかと、考えなかったわけではない。
だが、竜詩戦争は終わったのだ。竜を狩る者の筆頭として戦いを導いてきた男、何より邪竜ニーズヘッグに肉体を奪われて槍と牙を民へと向けてしまった男は、竜との融和へと向かう祖国には不要である。そう考えての決断であった。
では、何処に行き、何を成すというのか?
エスティニアンは、その答えを導き出すための第一歩として、追悼の旅を続けてきた。
生まれ故郷、ファーンデールの跡地に赴き、父と母、そして弟アミニャンに祈りを捧げた。
皇都を望む高台に立ち、親友と相棒の命を救ってくれた騎士にも礼を述べた。
さらには、罵り合いながらも共に旅し、自分たちの進路を拓くために散っていった女のために魔大陸へと赴き、花を手向けさえした。
かつての自分であれば、絶対にしなかったであろう旅だ。
その終着点に選んだ場所で、姿なき詩竜に言葉を投げかける姿を、あろうことか聖竜に見られたのである。
「七大天竜ともあろう者が、のぞき見とは趣味が悪い」
照れ隠しに憎まれ口を叩く竜騎士の姿を見て、聖竜は顔を歪める。微笑んだのだ。
『邪魔だったか、蒼の竜騎士よ。だが、その花と想いに感謝すべきだと感じたのだ。
妹たるラタトスクは、もはや竜詩を紡ぐこともできぬ身なれば、
我が成り代わり、想いを伝えるほかあるまい』
一時は、邪竜の魂と融合し、その想いを我が物として感じたことのあるエスティニアンだ。
ニーズヘッグとフレースヴェルグが、いかに血を分けた妹竜を掛け替えのない存在と思っていたのか嫌というほど知っている。だからこそ、その聖竜の意思に救いを感じた。
「そうかい……ありがとうよ。だが、俺はもう蒼の竜騎士じゃあない。
竜騎士の役割を演じる必要はない、もう終わったのさ」
それは素直な想いである。だが、聖竜は彼が背負う得物を見逃してはいなかった。
『そう言うわりに、我が兄弟の魔力を帯びた竜槍を手放しておらぬのは何故か?』
問われて、はたと気づいた。皇都を出る決意をしたあの時、確かに自分は竜騎士の甲冑一式を置いていこうと決意していた。しかし、邪竜ニーズヘッグの力で変異したこの槍だけは、手放すという発想すらしなかったのだ。
答えに詰まるエスティニアンを見て、聖竜はふたたび意思を発する。
『お前には、まだ戦う理由があるということだ。
役割は終わったと言いながら、まだ完全に終わったとは思えていない』
そうなのかもしれない。
まだ完全な決着はついていないのではないか。竜を屠るためだけに研ぎ澄まされてきた、この槍術が必要となることが――蒼の竜騎士ではない今の自分に成すべきことが――あるのかもしれない。
『蒼を捨てた竜騎士よ、人と竜の双方のために歩むと、その槍に誓うのならばついて来い。
竜と共に生きる、真の竜騎士に相応しい鎧を与えてやろう』
欠けた翼を広げて、大空へと舞い上がる聖竜を呆然と見上げていたエスティニアンは、我にかえると駆け出し、単座式飛空艇に飛び乗った。
しばしの飛行の後、辿り着いたのは「ソール・カイ」の外れにある遺構であった。どうやら、竜と人との蜜月時代に築かれた飛竜留めのようだ。
その一角に聖竜は降り立つと、奥へと進むように促した。
そして、エスティニアンは、それを見つけた。
「こいつは、驚いたな……」
人のために建てられたものであろう兵舎らしき遺構の室内には、いくつもの鎧櫃が並んでいる。多くが朽ち果てていたが、竜の魔力によって保たれていたのか奇妙な程に綺麗な櫃が、ひとつだけ遺されていたのだ。
開けてみて、さらに驚愕した。
『かつて竜騎士とは、竜と共に戦う者のことを示していた。
我が妹、ラタトスクもまた、人の騎士を背に乗せることを好んだ。
彼らがまとう鎧に加護を与えるほどにな』
鎧櫃の中には、紺碧の美しい甲冑一式が二揃い並べられていた。
『そこに残るふたつの鎧は、本来であれば次にラタトスクの背に乗る者たちに与えられるはずだった。だが、力を与えるほどに、欲深き者はさらなる力を求めるもの……
鎧よりも、その力の源を欲した愚か者が現れたのだ。
その後に起こったことは、承知であろう?』
人の王トールダンが配下の十二騎士と共に詩竜を惨殺し、魔力の根源たる「竜の眼」を奪い、喰らったのだ。
使われることのなかった、最後の竜騎士の鎧。ただそれを見つめながら、振り返ることもなくエスティニアンは問い返した。
「ならばなぜ、俺にこの鎧を……戦う力を与えようとする?
俺もまた、欲深き愚か者のひとりなのかもしれないんだぞ!?」
数秒の沈黙の後、フレースヴェルグは答えた。
『……ふたたび人を信じてみようと思わせてくれた娘がいたのだ』
聖竜は続ける。
『身につけられるどころか、名すら与えられずに残された鎧だ。
蒼を捨てながら、新たな蒼を受け継ぐ気があるならば、持ってゆくがいい』
しばしの後、エスティニアンは古の兵舎の中から、太陽の下へと歩み出た。
深き蒼をまとって。
「この鎧に名がないというなら、俺が与えよう」
魔力を宿した眼を細めて、聖竜は竜騎士を見つめる。
「こいつの名は『アイスハート』だ。
蒼の竜騎士の称号を捨てながらも、未だ怨念にまみれた魔槍を持つしか能のない男。
その行く末を見守るには、相応しい名だろうさ」
エスティニアンの言葉を聞いて、聖竜は盛大な咆哮を発してみせた。
あるいはそれは、竜の笑いであったのかもしれない。

かくして新たな鎧を得た竜騎士エスティニアンは、雲海を後にした。
真の決着をつけるため、そして、歩み続ける相棒たちの道を切り開くために。
そして時は流れた。
エスティニアンは今、ギラバニア湖畔地帯を臨む岩山に立っている。眼下には城塞都市「アラミゴ」に向けて進軍する兵の列が長々と続いている。きっと、あのどこかにイシュガルドの軍勢を率いる親友や、かつてともに戦った相棒と少年たちも含まれているのだろう。
帝国の巨砲を破壊することで道は拓いた。ならば、圧政者たちを打ち払うのは、頼もしき彼らに任せておけばいい。
彼に残された使命は、もうひとつあるのだから。
だが、微かな残滓さえ残されていないソレを見つけるのには苦労をさせられた。
結局のところ、友たちが戦う様をただ眺めることなどできず、密かに同盟軍の側面を突こうとしていた帝国軍の飛行型魔導アーマー部隊を叩き落としていた彼は、やがて王宮方面の空に、懐かしささえ覚える魔力を感じることになる。
急ぎ撃破した魔導アーマーの残骸から槍先を引き抜いたエスティニアンは、勝敗が決しつつあった戦場を駆け抜けた。だが、アラミゴ王宮の空中庭園へと辿り着いた時には、すべてが終わっていた。
ただし、彼の使命だけは、まだ残されている。
ゆっくりと、咲き誇る異国の花々を踏みしめて、彼は歩んだ。
「やれやれ、手間をかけさせやがって……。
蛮神の核に使われたことで、エーテルの残滓すら失われたか……。
どうりで、まったく感じ取れないわけだ……」
エスティニアンは、背負っていた槍を手にした。魔槍「ニーズヘッグ」、かつて自分でもあった竜の名を与えた槍の穂先をソレに向ける。
「とはいえ、このままにもしておけん」
力と魔力を込めて貫き、破壊する。
もはや抜け殻同然であった竜の眼は、黒き霞となって、紅蓮の空に散っていった。
「本当にさよならだ、ニーズヘッグ」
こうして蒼を捨てた竜騎士、エスティニアンの追悼の旅は終わった。
真の意味で決着を付けた彼は、ようやく新たな一歩を踏み出すことができるのだ。
彼が歩む先の空が、晴れ渡る蒼か、暮れゆく紅か、あるいは宵闇の黒なのかはわからない。
だが、どんな空の下であっても、彼は人と竜のために暗き魔槍を振るうことだろう。